タイル浮きの補修はどうすればいい?調査方法と補修方法を併せて解説
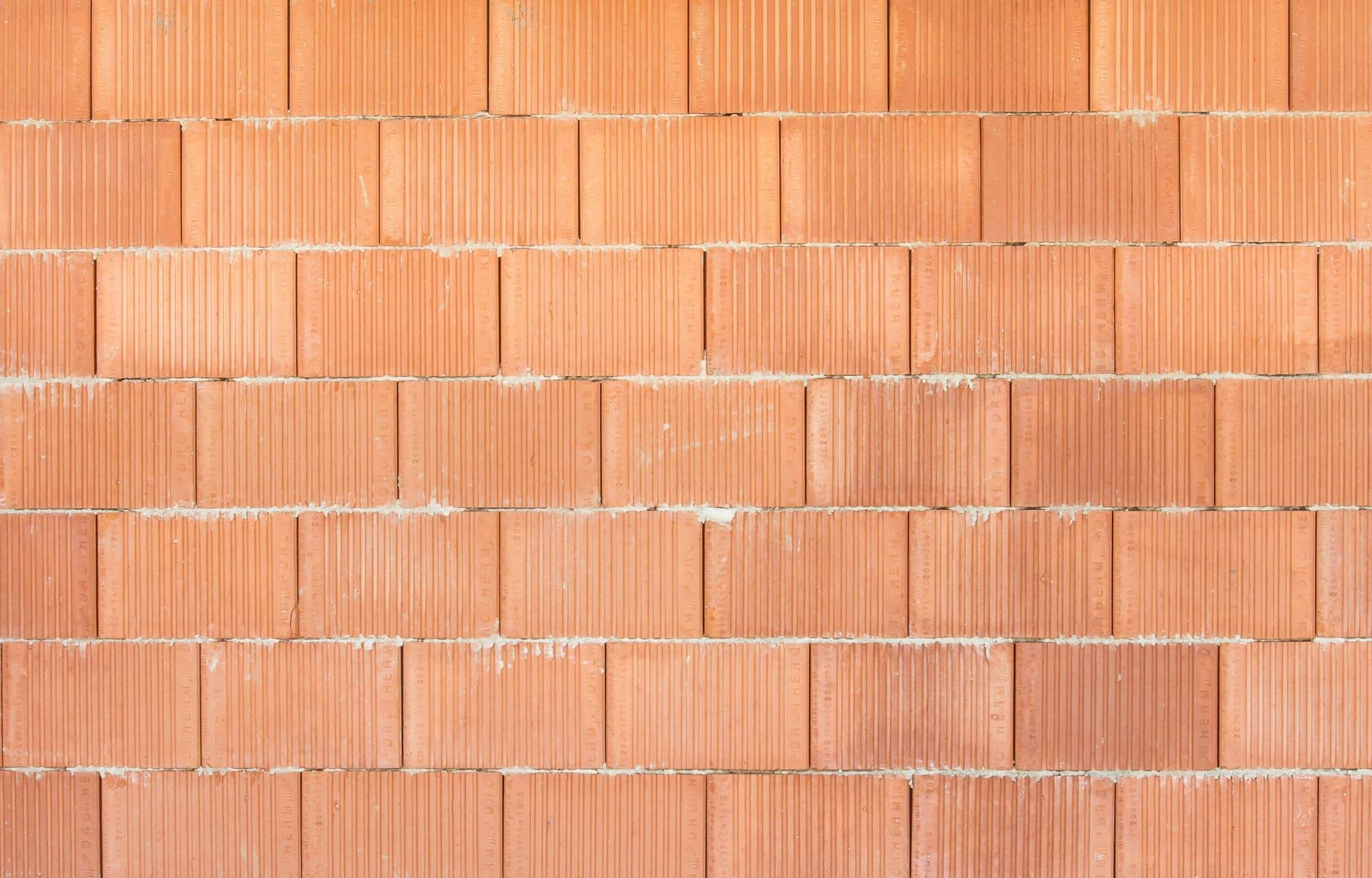
外壁のタイル浮きについて不安を感じている建物所有者の方も多いのではないでしょうか。タイルの浮きは、下地材との接着力低下によって起こる深刻な問題です。
放置すると突然の落下事故や雨漏りを引き起こし、建物の資産価値にも悪影響を及ぼす可能性があります。
しかし、タイル浮きの種類や調査方法、適切な補修工法の選び方など、判断に迷う点が多いのも事実です。
この記事では、タイル浮きの基礎知識から調査・補修方法、費用相場まで詳しく解説します。
タイル浮きとは?

タイル浮きとは、外壁に貼られているタイルが主に下地材から部分的に剥がれてしまい、浮いている状態のことを指します。
コンクリートやモルタル、さらには金属系下地など、施工されている土台(下地)とタイルの接着力が低下すると、振動や気候変化によってタイルが徐々に剥がれかけることがあります。
このタイル浮きを放置すると、ある日突然タイルが一気に落下して事故が発生する可能性もあり、軽視できない問題です。
建物の美観が損なわれるだけでなく、防水機能の低下によって雨漏りのリスク増大など、建物全体の安全性や資産価値に影響を及ぼします。そのため、定期的な点検と早めの補修が極めて重要です。
タイル浮きの種類

タイル浮きには、いくつかの種類があります。
いずれのケースでも、気付かないまま長期間放置すると被害が拡大する恐れがあるため、浮きの性質をよく理解しておくことがメンテナンスのポイントです。
下地浮き
下地浮きとは、タイルを貼るためのモルタルや接着剤とコンクリート躯体との間に隙間が生じる状態のことです。
コンクリート面に油分やホコリが付着したまま施工されたり、経年による温度変化・振動などが重なったりした結果、タイルを貼る「下地」そのものが浮いてしまう場合があります。
下地浮きが広範囲に及ぶと、外壁が大規模に剥落するリスクが高く、早期段階で気付けないと修繕費用が膨れ上がることが多いため注意が必要です。
日常的には目視で発見しづらいため、打診調査などの適切な方法で定期的に確認する必要があります。
陶片浮き
陶片浮きは、タイル自体が下地から部分的に剥がれている状態を指します。
タイルの表面(陶片部分)に小さな亀裂が入ると、内部に水分が浸透しやすくなり、凍害やアルカリシリカ反応によって下地モルタルとの結合力が弱くなることが原因です。
一見するとタイル全体がしっかり張り付いているように見えても、軽く叩くと音が変わってくるため、定期的な打診が有効です。
陶片浮きがあるまま放置すると、局所的にタイルが割れて剥落する危険が高まります。
複層浮き
複層浮きは、コンクリート躯体とモルタルの間、あるいはモルタルとタイルの間など、複数の層で同時に浮きが生じている状態を示します。
いわゆる「二重三重の浮き」が発生しており、単なるタイル材の交換だけでは対処しきれないケースも多いです。
施工不良や経年劣化、振動・地震の影響など、複数の要素が重なり合うと複層浮きに発展しやすくなります。
この状態を放置すると、タイルの全面剥離にまでつながりかねないため、特に注意が必要です。
タイル浮きを調査する方法

タイル浮きが疑われる場合や、定期点検を行う際には、いくつかの調査手段があります。
建物規模や立地条件、求める精度などに合わせて最適な方法を選定することで、時間とコストのバランスを取りながら正確な診断を行いやすくなります。
目視調査
目視調査は、外壁などを直接見て異常がないかを確かめる最もシンプルな方法です。
表層に大きなひび割れや欠けがあれば把握しやすい反面、下地が浮いているかどうか、タイルの中間層が剥離しそうになっているかどうかは判断が難しくなるケースが多いのが特徴です。
とはいえ、誰でも気軽に行える調査方法なので、月に一度や季節ごとなど、定期的に見回りを行うだけでも早期発見につながる可能性が高くなります。
見つかった異常を写真やメモで記録し、専門業者に相談するきっかけにすると良いでしょう。
打診調査
打診調査は、タイルを軽く叩いて音の違いを確認する方法です。
浮きがない場合はどっしりとした音が返りますが、浮きがある場所は空洞音や甲高い響きになりやすいため、タイルの剥離具合をかなり正確に把握できます。
ただし、建物全体を網羅するには専門的な調査が必要となり、人手と時間がかかります。
赤外線調査
赤外線調査は、タイルが下地から浮いている場合に、空気層が断熱材のような役割を果たすため、健全部位との温度差が生じやすくなるのが特徴です。
ただし、湿気や日射の影響を受けやすく、条件によっては正確な判別が難しいこともあります。
広範囲を短時間で調査できる利点があり、特に大規模建物や高層物件ではドローンと併用すると効率良く調査を行えます。
ただし、正確な診断には気温や天候条件を考慮する必要があり、日射の有無や時間帯を選ぶことが大切です。
また、赤外線の情報だけでなく、追加の打診調査などを組み合わせて補完的に解析することが推奨されています。
タイル浮きの補修方法

タイル浮きの発生が確認されたら、状態や原因に合わせて最適な補修工法を検討する段階に移ります。
補修方法によって施工期間や費用が大きく変わるため、事前に複数社から見積もりを取得して比較検討すると良いでしょう。
| 補修方法 | 特徴 |
|---|---|
| アンカーピンニング工法 | 浮きが出ている部分へ孔を開けて樹脂を注入し、アンカーピンでしっかり固定する方式 |
| エポキシ樹脂注入工法 | 剥がれが広がる前に、タイルと下地の間に注入口をつくりエポキシ樹脂を流し込む手法 |
| タイル除去Uカット工法(ひび割れに対しての工法) | 浮いたタイルを完全に除去し、下地をU字状に切り出した上で補修材や接着剤を詰め、新たにタイルを貼り直す方法 |
| 張替え工法 | 浮いている箇所だけでなく、その周辺タイルを含めてまとめて撤去し、新しいタイルを全面的に貼る方式 |
| 外壁複合改修工法 | タイル浮きだけでなく、建物全体の外壁を一体化させる大規模補強手法 |
アンカーピンニング工法
アンカーピンニング工法は、タイルの浮き箇所に穴を開けて樹脂を流し込み、そこにアンカーピンを差し込むことで固定力を高める補修手段です。
樹脂が硬化し、アンカーピンがしっかり噛み合うと、浮き部分が再度強固に押さえつけられる仕組みになっています。
大規模マンションやビルの外壁浮きにしばしば用いられ、樹脂の硬化が完了した後は、ピンの表面を既存のタイル目地に似た色で仕上げるため、見た目の違和感を最小限に抑えることができます。
打診調査などで確認した浮き箇所ごとに施工するため、ピンを打ち込む場所を誤らないよう、正確な調査データが重要です。
エポキシ樹脂注入工法
エポキシ樹脂注入工法は、タイルの剥がれかけた部分へ専用の注入口を設け、そこから高粘度または低粘度のエポキシ樹脂を注入し、下地とタイルを再び一体化させる方式です。
樹脂が隙間を埋めることで浮きが解消し、硬化後は高い接着力が得られます。
ただし、タイル全体が大きく浮いている場合や、ひび割れが複数箇所に及ぶ場合は、一度に広範囲を対応するのが難しいケースもあります。
部分的な浮きや小規模補修には手軽な方法ですが、複層浮きなど深刻な状態の場合は、他の工法との併用も検討しましょう。
タイル除去Uカット工法
タイル除去Uカット工法は、ひび割れに対しての工法となり、その箇所のモルタルやコンクリートをU字形状にカットした上で、シーリング材やエポキシなどを充填してタイルを再施工するやり方です。
下地まで割れている部分を根本的に再生したい場合には適しており、下地の状態を確かめながら補修を進められます。
ただし、タイルの張り替えは既存タイルと同じ製品が入手できない事がほとんどとなり近似色で対応するため、色やデザインが多少異なるものを使わざるを得ないこともあり、外観の統一性に影響が出る可能性も考えられます。
張替え工法
張替え工法は、浮いているタイルを含め、その周辺までまとめて撤去して新たにタイルを貼り直す方式です。
下地をしっかり整えた上で新規のタイルを貼り付けるため、仕上がりは美しく、安全性も高い一方で、施工範囲が広がるほど費用が大きくなるデメリットがあります。
しかし部分的な張替えだと、既存部分との色合いの違いが目立ってしまうケースもあるため、事前の試験張りや在庫確認が重要です。
外壁複合改修工法
外壁複合改修工法は、下地材とタイルの間にアンカーピンを多数打ち込み、表面に繊維ネットなどを固定して一体化させることで、既存外壁を大規模に補強する手法です。
ピンネット工法と呼ばれることもあり、タイル浮きだけでなく、今後発生するリスクに対しても一括して対処しやすいのが利点です。
既存のタイルを大部分残したまま補強するため、解体の手間を軽減しつつ安全性を高めることができます。
ただし、専門知識と施工技術が必要であり、工事費も比較的大きくなるケースが多いです。そのため、対象となる建物の規模や劣化度合いを十分に考慮しながら導入を検討する必要があります。
タイル浮きの調査・補修にかかる費用相場

タイル浮きを解消するためのコストは、調査から補修までの全体的なフローによって大きく変動します。
建物の規模、施工箇所の高さ、使われる工法、足場の有無など多角的な要因を総合して、トータル費用が決定されます。
調査にかかる費用
足場を組まずにロープアクセスなどで行う場合、数万円~十数万円程度で済むケースがあります。
一方、ビル全体を足場で覆う場合は、その設置と解体のコストだけで数十万~百万円規模になることもあります。
ドローンを使用して高所から外壁を撮影する場合や地上からカメラを向ける場合など、赤外線調査を用いるケースでは、数十万円程度が目安になりやすいです。より精密な解析を行う場合や大規模物件では、さらに高額になることも珍しくありません。
いずれにしても、まずは専門業者の現地調査やヒアリングを受けて、見積もりを複数取得するのが賢明です。
補修にかかる費用
工事範囲や施工難易度、選択する工法によって費用が大きく異なります。
エポキシ樹脂注入工法やアンカーピンニング工法であれば、一箇所数千円台~数万円台で済むこともあります。
一方、タイル除去Uカット工法や張替え工法の場合、タイルを撤去して新しいタイルを貼り直す必要があり、広範囲に施工が及ぶと費用が高額になりやすいです。
工賃や材料代の他、既存タイルの廃材処理費用も考慮に入れる必要があります。
外壁複合改修工法の場合、大規模な補修と安全性の向上を両立できる一方、工期や資材コストがかかるため、総額が数百万円単位に上るケースも珍しくありません。
足場を組むか組まないか、あるいはロープアクセスを活用するかどうかで、工事費の見積もりは大きく変わります。
まとめ
この記事では、タイル浮きの種類や調査方法、補修工法、それらにかかる費用相場について解説しました。
タイル浮きには下地浮き、陶片浮き、複層浮きなど複数の種類があり、状況に応じた適切な診断と対策が必要です。
調査には目視・打診・赤外線といった方法があり、建物の規模や状態によって最適な手法を選択することが重要です。
補修費用は工法や範囲によって大きく異なるため、複数の業者から見積もりを取得して比較検討することをおすすめします。
Takaoプランニングは、オフィスビルや集合住宅、病院など、さまざまな調査実績を持つ外壁調査・補修業務を専門に取り扱っている業者です。
最新の診断技術と豊富な経験を活かし、タイル浮きの調査から補修までをトータルにサポートいたします。
目視・打診調査から赤外線調査まで、建物の状況に応じた最適な調査方法をご提案し、正確な診断結果に基づいた効果的な補修計画を立案します。
タイル浮きに関する豊富な実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
